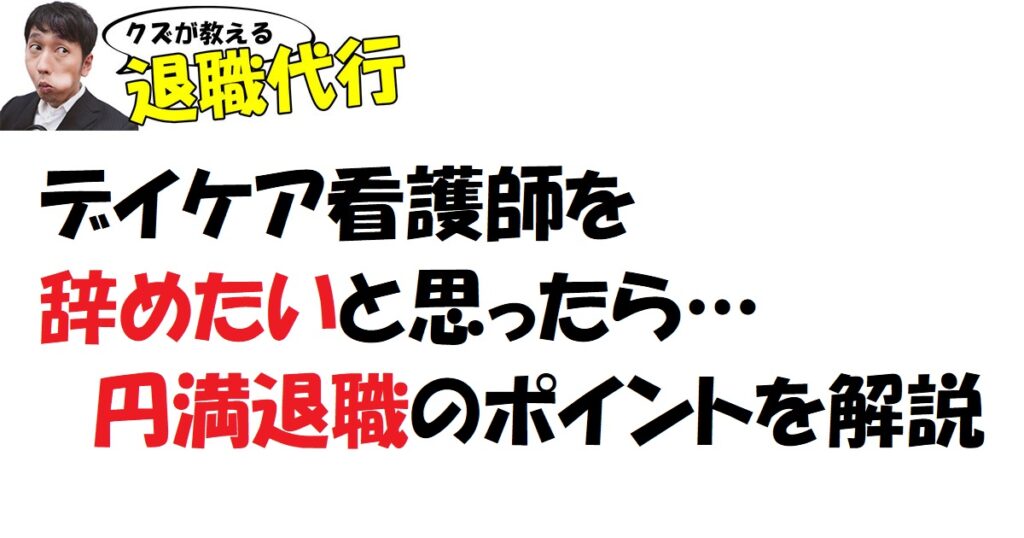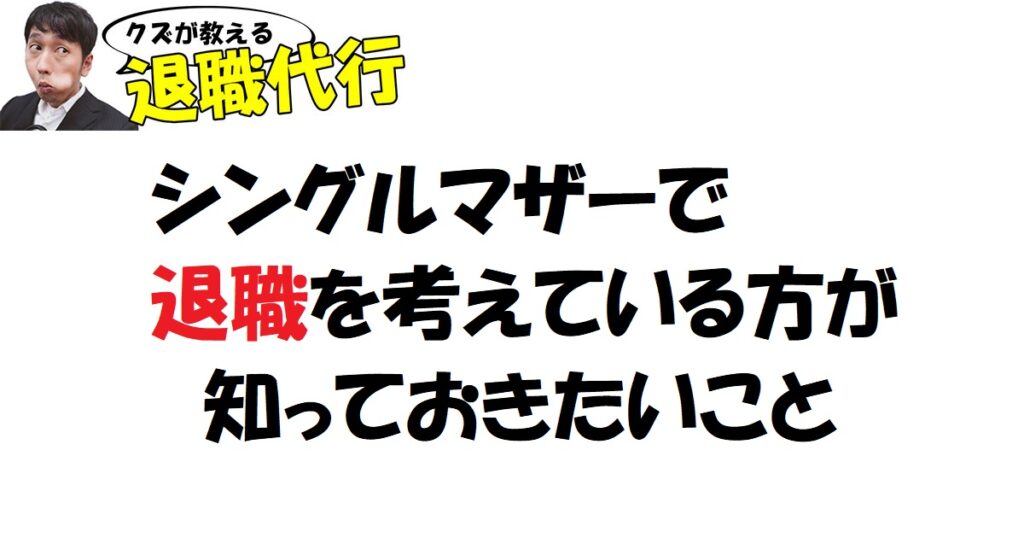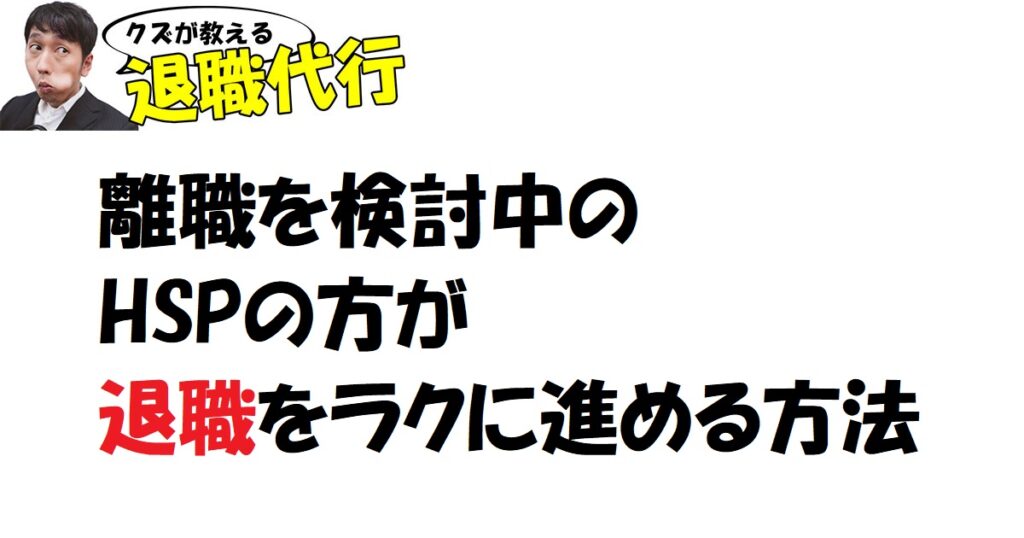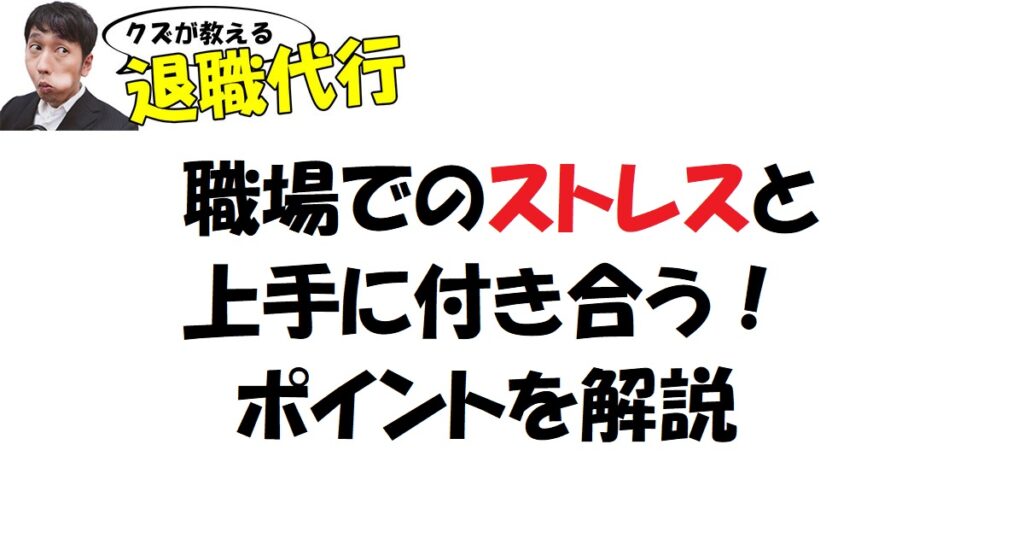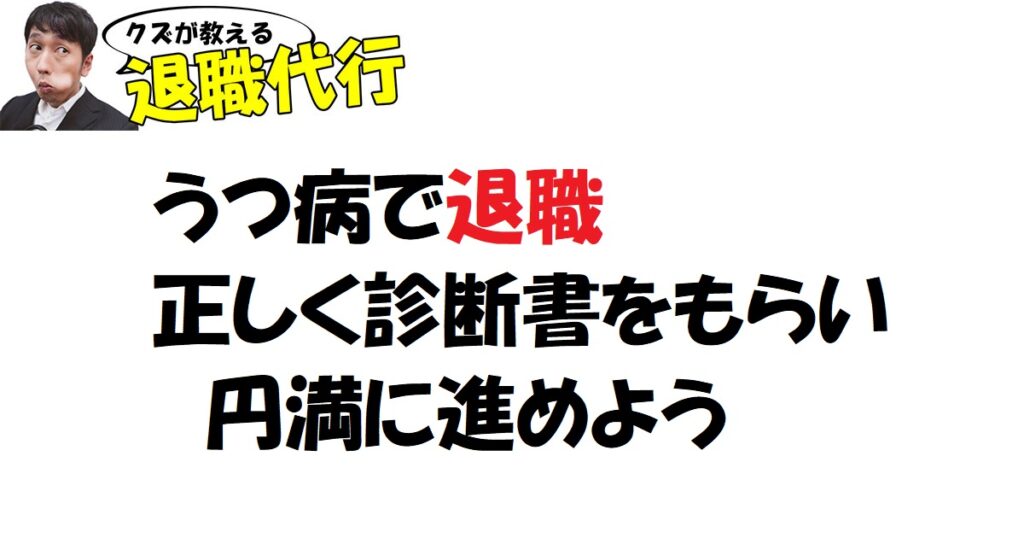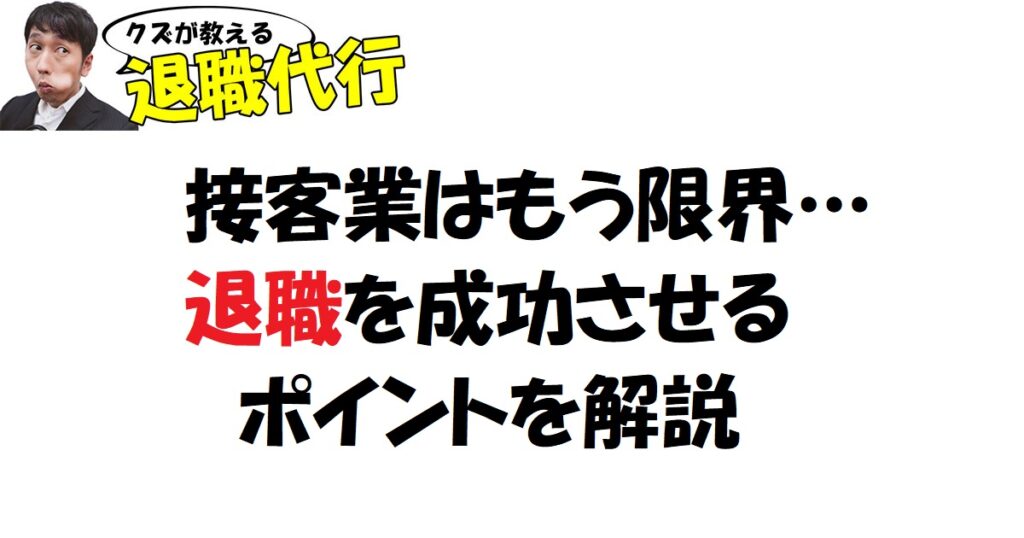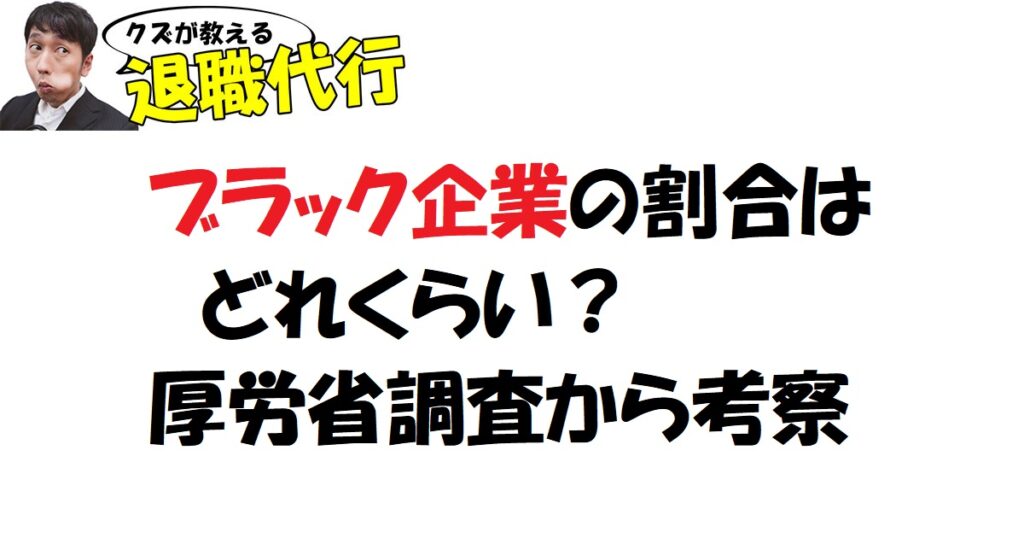
ブラック企業が多いとは耳にするのの、実際の数値を把握している人は少ないかもしれません。実数は、法令違反しているブラック企業の特徴を理解するとともに、法に抵触する項目を調べると見えてきます。業界ごとの件数を把握できれば、過酷な労働環境の背景を推測できそうです。
この記事では、厚生労働省のデータをもとに国内のブラック企業が犯している法令違反件数や、業界ごとの割合について解説します。
ブラック企業の割合と法令違反の件数
ブラック企業を数値化するにあたり、1つの指標となる国の調査があります。それは、厚生労働省労働基準局が行った調査活動を毎年まとめている労働基準監督年報です。
ここでは、同調査の報告を用いてブラック企業の割合や法令違反の件数を解説します。
ブラック企業の割合
ブラック企業の割合は、労働基準監督年報の定期的な立入検査数と違反件数で算出できます。最新版である令和2年の報告では、全体の約70%が何らかの法に抵触していることがわかりました。
ブラック企業の法令違反の件数
同じく労働基準監督年報から法令違反の件数を見ると全体で80,335件で、項目ごとに見ると詳細な違法内容がわかります。
この年報は多様な判断基準で構成されており、業種ごとの特徴を捉えることも可能です。
(参考)厚生労働省「令和2年 労働基準監督年報」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/r02.pdf
ブラック企業の定義
ブラック企業と聞くと過酷な職場のイメージが湧きますが、そもそもの定義を知らない人が多そうです。普段は当たり前に思っている労働環境が、法令違反にあたるケースもあるかもしれません。
ここでは、厚生労働省がまとめている特徴について解説します。
ブラック企業の定義
厚生労働省は、ブラック企業について定義していないものの特徴を以下のようにまとめています。
”① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、など”
(引用元)厚生労働省「確かめよう 労働条件」Q&A
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/zenpan/q4.html
それぞれについて細かくみていきましょう。
①:労働時間は1週間で40時間、1日で8時間を超えてはならないとされています。残業や休日出勤が多い職場は、違法となるので注意が必要です。また、極端なノルマを課して労働者を追い込む会社もブラック企業と言えます。
②:労働の対価である賃金を支払ってくれないことや、言動での嫌がらせが常態化している状況です。パワーハラスメントとは「ノルマがクリアできないなら自腹を切れ」「目標に達しなければ給料カット」等の不当な扱いのことをいいます。
③:労働者に不本意な転勤をさせたり、自主退職に追い込んだりする行為のことです。あくまでも本人が希望したという体にするため、辞めさせたい社員にハラスメントを行います。仕事を与えないなどの方法で、嫌がらせを行う会社もあるようです。
労働基準監督署における監督指導等の状況
ブラック企業の定義を理解したら、実際の指導監督状況が気になるところです。法に触れている項目がわかると、日本の職場の問題点が見えてくるでしょう。
ここでは、労働基準監督署における法令違反項目や件数について解説します。
立入検査の実施数と法令違反数
労働基準監督署では「定期監督」の名称で、毎年現場に出向き立入検査を行っています。対象となる企業は、違反しているかどうかにかかわらず厚生労働省の方針に基づいて選ばれる事業場です。
令和2年の立入検査実施数116,317件のうち法令違反は80,335件で、全体の69.1%が法に触れているといえます。次章では、違反が多い項目について詳述します。
法令違反が多い項目
法令違反項目は、労働基準法並びに労働安全衛生法のいずれかに接触していることが多いです。労働基準法は、休日や賃金など実際の労働環境の観点から雇用者を守る法律のことをいいます。労働安全衛生法は、働く人々を健康面から守ろうという位置付けの法律です。
労働基準法の法令違反件数は、以下の通りです。
- 労働時間 19,493件
- 割増賃金 16,710件
- 労働条件の明示 10,817件
- 賃金台帳 9,893件
- 就業規則 9,088件
一方の労働安全衛生法の法令違反項目と、件数は以下の通りです。
- 安全基準 22,432件
- 健康診断 20,153件
- 労働安全衛生規則 19,171件
- 時間把握 5,607件
- 衛生基準 4,148件
次項では、項目ごとの内容を詳しく解説します。
法令違反が多い項目の具体的な内容
まずは、労働基準法の法令違反項目について解説します。
・労働時間
先述した通り、労働時間は原則週40時間・1日に8時間を超えてはならないとされています。業種によっては待機時間の発生での残業や、緊急対応での休日出勤のケースもカウントされるでしょう。
・割増賃金
時間外労働分の賃金を、会社が通常の25%増しで労働者に支払わなければならないという決まりです。休日労働にも適用されるため、適切に給与を支払っていないと違反となります。
・労働条件の明示
会社が労働者に対して給料や労働時間などに関する取り決めを交付することです。口約束ではなく書面に契約内容を残し、トラブルを未然に防ぐ必要があります。
・賃金台帳
労働者への給料の支払い状況を記録しておくものです。記載すべき事項を一定期間保管しておかないと法令違反となります。
・就業規則
会社内のルールの作成や届出の義務に関する項目です。社内の決まりを従業員に周知していないことも、法に抵触します。
次に、労働安全衛生法の法令違反項目について解説します。
・安全基準
機械や設備を事故なく操作するための決まりを広範囲で記した項目です。危険防止のための周知や、点検不足の場合も違反となります。
・健康診断
正社員に健診を受けさせないといけないという内容です。会社は診断を受けさせたくても、労働者が忙しいことを理由に拒否した場合は罰則となります。
・労働安全衛生規則
快適で安全な職場づくりを目的とした項目です。ハラスメントや長時間労働など、近頃盛んに取り上げられる労働災害の解消を目指す位置付けとなります。
・時間把握
働いた時間をタイムカードなどの客観的に記録できる方法で保管するという内容です。賃金台帳だけでは不正申告の可能性があり、労働者の精神疾患や過労死を防ぎ切れないため2019年より義務化されました。手書きで勤怠管理をしていた会社が、デジタルな記録方法を導入せず違反となるケースも考えられます。
・衛生基準
労働環境に関する決まりを記した項目です。作業場や休憩所の配置などについても記載されており、適切な設備が備えられていない場合は違法となります。
ブラック企業の業界ごとの割合は?
業界ごとに働き方は異なり、業界によりブラック企業になりやすい特徴が存在します。先述の違反項目と照らし合わせると、労働環境の傾向がわかるかもしれません。
ここでは、ブラック企業の業界ごとの割合を解説します。
ブラック企業の業界ごとの割合
ブラック企業の業界ごとの割合は、以下の通りです。
- 印刷・製本業 80.3%
- 家具・装備品製造業 79.3%
- 金属製品製造業、農業 78.7%
- 旅館業 78.5%
- 飲食業 76.9%
これらの業界は、なぜブラック化しやすいのでしょうか。
・印刷・製本業
いかなる場合でも取引先の都合に合わせなければならないという特徴があります。時間外労働をせざるを得ず、結果的に働きすぎるという背景が考えられるでしょう。
・家具・整備品製造業
景気によって長期時間労働を余儀なくされるケースがあります。働きすぎは集中力低下による労働事故や、健康被害に繋がりかねません。
・金属製品製造業
機械を扱う作業が多く安全基準点検を日頃から行う必要があります。チェック項目は多いですが、確認を怠ると大きな労働災害につながりやすいです。
・農業
収穫の時期を迎えると、朝から晩まで作業しなければならないことや休憩が取りにくいという特徴があります。体力を使う仕事でもあり、適切に休めないと体調を崩しかねません。
・旅館業
従業員不足の職場が多い上、交代勤務が基本です。不測の事態が起きると、連続シフトになりスタッフに負荷がかかってしまうことが考えられます。
・飲食業
慢性的な人手不足で時間外労働が多いにもかかわらず、残業代が出ないケースが多いです。特に正社員は業務の範囲が広く、パートやアルバイトで賄えない部分を自らがカバーしなければなりません。
まとめ
この記事では、ブラック企業の割合を知りたい人向けに以下のようにまとめました。
- 厚生労働省が基準とするブラック企業の3つの特徴を把握する
- 労働基準監督署が発行する年報から算出可能
- 令和2年の調査では、日本企業の70%がブラック企業といえる
- 立入検査の最多違反項目は「労働時間」と「安全基準」
- 法令違反項目が最も多い業界は「印刷・製本業」
ブラック企業の割合を算出する際に必要なのは、労働基準監督年報などの信頼性のあるデータです。国の判断基準を押さえた上で、法令違反件数を項目・業界別に見ると日本企業の特徴を大まかに把握できます。
定期的に発表される統計をもとに、近年の労働環境の傾向を掴みましょう。